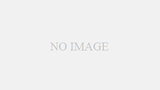国際金融の世界に、「ハード・カレンシー」という用語があります。
これは、当社社長による著書からの引用で恐縮ですが、「その通貨の発行国に留まらず、国際的な商取引・資本取引等において広く利用されている通貨であり、為替取引等においても法的・時間的制約が少ないもの」のことです。
つまり、ハード・カレンシーとは、平たく言えば、「どこでも交換できる通貨」「使い勝手の良い通貨」のことです。特に、ドル、ユーロ、円、ポンドは国際的にも重視されている通貨ですが、このことを実際の数値で検証してみましょう。
追記:2016/09/09
2016年9月9日付で、人民元とSDRに関する当社レポートを公表しておりますので適宜ご参照ください。
▼ ストック面
通貨(お金)には様々な機能がありますが、中でも「決済機能」(フロー)と「価値の保存機能」(ストック)が大事です。このうち、ストック面では、例えば各国の中央銀行が準備通貨としてどの通貨を保持しているかというデータが参考になります。国際通貨基金(IMF)の「公式外貨準備世界通貨構成 」(World Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, COFER)によれば、2015年第Ⅰ四半期末において、通貨構成別内訳が判明するのは全体の52.72%であり、準備通貨の比率は次の通りです。
<IMFによるCOFERの2015年第Ⅰ四半期末のシェア>
1位…米ドル、32.1%(60.81%)
2位…ユーロ、12.8%(24.33%)
3位…日本円、2.1%(3.93%)
4位…英ポンド、2.0%(3.86%)
5位…豪ドル、1.0%(1.90%)
※ただしカッコ内の数値は、世界の外貨準備高のうち内訳が判明しない部分についても、内訳が明らかな部分と同じ構成割合だったと仮定したシェア。
▼ フロー面
次に、フロー面では、外為市場における取引高が参考になります。国際決済銀行(BIS)が3年に1回公表するレポート「Triennial Central Bank Survey」の2013年4月版 (Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results, September 2013)のP5によれば、世界の外為市場において圧倒的なシェアを占めているのは米ドル(87%)ですが、これにユーロ(33%)、円(23%)、ポンド(12%)、豪ドル(9%)が続きます(但し為替市場におけるシェアを示しているため、全ての通貨のシェアを合算すると100%ではなく200%になります)。
<BIS統計による2013年4月時点の外為シェア>
1位…米ドル、87.0%
2位…ユーロ、32.4%
3位…日本円、23.0%
4位…英ポンド、11.8%
5位…豪ドル、8.6%
▼ 人民元
ところで、最近、国際的な資本市場で急速に存在感を強めている人民元は「ハード・カレンシー」と呼んでも良いのでしょうか?
すでに人民元は「ハード・カレンシー」である、と主張する人の論拠は大きく分けて二つあります。その一つは、昨年、中国の通貨・人民元が国際通貨基金(IMF)の「特別引出権」(SDR)の構成通貨に含められたことです。また、もう一つは、国際的な商取引における人民元のシェアが高まりつつあることです。国際的な決済電文組織である「SWIFT」のページによると、確かに国際的な商取引(SWIFT電文)における人民元の決済高は増加傾向にあります。
<SWIFTによる2015年10月時点の顧客送金決済・銀行間決済額のシェア>
1位…米ドル(42.38%)
2位…ユーロ(29.89%)
3位…英ポンド(9.05%)
4位…日本円(3.00%)
5位…人民元(1.92%)
ただ、当社としては、人民元が既に「国際的なハード・カレンシーとなった」と見るのは、まだ早いと考えています。というのも、ある通貨が「国際的なハード・カレンシーである」と呼べるためには、高度な決済システムと安定した法制度、さらに国際的な資本移動の自由が保証されていることなどが必要です。人民元は確かに国際的な商取引で急速に存在感を増しているものの、これらの観点からすれば、人民元の自由交換性は「まだまだ」だと言わざるを得ません。
後世になって、「IMFのSDRに人民元が含められたのは、IMFの判断ミスだ」と言われない、という保証はないでしょう。